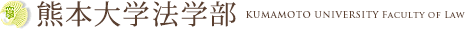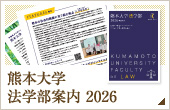- ホーム
- 学生・教員リレーエッセイ
- 太田 響陽(2024年10月28日)
2024.10.28 <太田 響陽(2024年10月28日)>
太田 響陽(法学部3年)
2024年1月1日、石川県能登地方を、最大震度6強、マグニチュードにして6.9という大地震と、それに起因した津波や大規模な火災が襲いました。この震災と二次災害による死者数は、確認されているだけでも282名に上っています(2024年5月時点)。このエッセイでは、私が能登半島に滞在した4月18日から4月22日の5日間で経験したことについて、皆さんと共有します。
私は4月18日に熊本から出発しました。地図アプリなどで確認していただきたいのですが、金沢と能登地方との間にはかなりの距離があり、金沢から能登に向かう道中私は、能登に入るまで被害は見受けられないだろうと考えていました。しかし、震源地から100キロ以上離れた河北郡内灘町に入ったあたりから、震災の影響は顕著に表れ始めました。液状化現象によって地面が複雑に歪み、その歪みに沿うように電柱も家屋もブロック塀も歪んでいます(写真1)。その後に通った道で目にした、斜面の滑落によってガードレールの根元があらわになるほど削られた道(写真2)や、倒壊した家屋(写真3)など、言葉が見つからないとはこのことを言うのだと実感させられるほどの光景が広がっていました。
同日能登に入り、被害の状況を実際に確認するため、朝市で火災のあった輪島に向かいました。建物は鉄筋とコンクリートを残してほぼすべて焼け落ち、自動車のフロントガラスが溶けていることからも、火災の深刻さがうかがえました(写真4~7)。
2日目には、避難所から二次避難所への移転作業の一環として、二次避難所の設営作業を行いました。段ボールベッドを設置する作業を行いましたが、避難所も完全に無事な状態という訳ではなく、あちらこちらに亀裂が見られました。(写真8)
3日目には仮設住宅を訪問し、そこで生活されている方々とお話をさせていただきました。震災当日なにが起こっていたのかなど、詳しいお話を聞かせていただきました。
4日目にも海岸沿いの避難施設を訪問し、被災者の方々との交流を行いました。能登半島の海岸線沿いでは、大規模な隆起が発生しており、自然の驚異をまざまざと見せつけられることとなりました(写真9)。写真内の白い範囲は、すべて今回の地震で隆起したものだと言われています。
今回のボランティアを通して私が学んだことは、実際に自分の目で見て感じることの大切さです。今回掲載した文章でも写真でも、実際に目にした時に感じることの半分も伝えられていないと感じています。また、被災地の状況も、良い意味でもそうでない意味でも刻一刻と変化していきます。このエッセイを書いている最中にも、石川県では記録的な豪雨災害が発生しており、実際に訪問させていただいた街も凄惨な被害を受けています。日本は災害大国であり、いつどこで地震、豪雨などの被害が起こっても不思議ではありません。だからこそ、メディア報道に映し出される写真や映像だけではなく、実際の状況を自分の目で見て、自分で何かを感じ、考えることこそが重要ではないかと考えます。
●ここから下には、令和6年能登半島地震の被災地の写真を掲載しています。