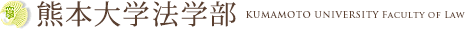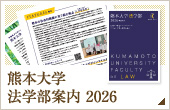- ホーム
- 学生・教員リレーエッセイ
- 横塚 志乃(2025年7月9日)
2025.07.09 <横塚 志乃(2025年7月9日)>
「日本社会と世界のマイノリティ問題」というテーマで、3・4年次向けゼミを開講しています。
文献や裁判ケースなどを読んでマイノリティ問題を学ぶこともしておりますが、それ以上に当事者の現場からの声を聞くことも問題を多角的に考えるのに非常に大事だと思っており、ゲストスピーカーを招いての講義も頻繁に行っております。SNSやメディアから情報を得ることも可能ですが、それ以上に現場からの声を聞くことも、メディアとのgapを発見することができたりし、その問題を多角的に考えることがより可能になると思っております。ゲストスピーカーをお呼びするにあたっては、一つの問題に対して本当に色々な解釈が存在するため、学生に複数の視点を知った上で、自分で最終的に考えて意見を持ってもらえるように心がけています。
また、一方的に教員やスピーカーの方の話を聞くレクチャースタイルではなく、アメリカ式の対話方式での授業をこのゼミでは心がけております。参加者の方の様々な考え方を知ることにより、学ぶことが多いと考えているためです。
2025年の前期のゼミでは学生自ら興味のあるテーマを選んでもらい、その専門の現場の方にゲストスピーカーとして来ていただいております。まだまだこの他にも学生の興味に合わせて現場学習やゲストスピーカーの方の講義が多く予定されております。
5/20のゼミ
在日クルド人と共に 温井立央様がオンラインで埼玉県の蕨市から参加していただきクルド人問題に関するお話と意見交換をしてくださいました。
6/17のゼミ
在日ウィグル人協会の田中サウト様がオンラインで東京から参加してくださり、在日ウィグル人の状況についてお話をしてくださいました。
6/24のゼミ
熊本市市長の大西様が対面でゼミに講義と意見交換に来てくださり、熊本地震を通して災害対応や避難所の実態、そして女性や性的マイノリティ、外国人といった社会的マイノリティの方々が特に災害の際に直面する課題についてお話をしてくださいました。
7/1のゼミ
南小国町議会議員の森永一美様が対面でゼミに講義と意見交換に来てくださり、学生たちが聞きたいといっていた政治の場に女性がどこまで意思決定のプロセスに声を届けられるのかという現状の課題や、女性議員の比率を伸ばすために世界で提案されているクオータ制の是非などについて意見交換をしたりしました。
7/8のゼミ
ウクライナとロシアの関係について興味があるゼミ生が複数いることからソ連・ロシアに関する有識者でいらっしゃる熊本出身の元NHKディレクターの馬場朝子様にお越しいただき、ロシアとウクライナの戦争の歴史的な背景について詳しくご説明いただきました。馬場さんは一般的に紛争はそれぞれの当事者から見た解釈は全く違うものになっており、双方の視点を理解できないことには真の解決へ辿り着くことが大変困難を極めるとお考えです。一般的な報道では触れられないロシアの目線から見るとウクライナとの戦争はどういう意味を持つのか、なぜ起こってしまったのかという視点をゼミ生にわかりやすく説明してくださいました。
学生たちにはゲストスピーカー講義のあと、感じたことをreflection paperに書いてまとめてもらっております。たくさんの気づきがあるようで、つい先日ゲストスピーカーとして来てくださった森永様からは、「学生さんの鋭い視点とアウトプット力に感動しました。事前に南小国のことを調べてからの質問、ご自身の今の活動に関することの質問、話の流れでの質問...いろんなバリエーションの質問があり、濃い、刺激的な時間でした。私が一番勉強になりました。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。」とメッセージをいただいたところです。
一番最近のゲストスピーカー講義では馬場さんのお話の後に、ウクライナとロシアについての状況を踏まえて「今の日本の状況をどう思われますか?」「馬場さんの考える報道のあり方について教えていただけますか?」「若い世代と上の世代ではプーチン政権に対しての考え方に温度差はあるのでしょうか?」など多くの質問があがり、積極的な意見交換が行われました。馬場さんからは「若い人にこういう話を聞いてもらう必要があると思っており、とても楽しい時間だった。」と言っていただきました。
法律、政治的イベント、歴史、紛争の解釈はさまざまな解釈が存在し、それぞれの立場や解釈を理解することが非常に重要になってくると思います。例えば紛争や戦争では対立する当事者間では全く異なる真実やストーリーが存在するため、多角的な視点から物事を考えられるようになっていただくことで、なぜこのような争いが生じているのか、問題の本質や根本的な理解ができるようになります。日本の教育では一方的に先生の話を聞くレクチャー方式が多いと思いますが、グローバル社会ではこういった自分で考え、自分の意見を発信していけることが必要不可欠です。ぜひ一緒に多角的に考える力を身につけていきましょう。